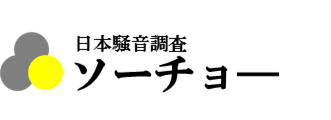騒音発生源特定推定の代表的な方法とその使い分け
騒音発生源の位置や強さ、などを特定する「音源同定」についてはさまざまな方法が検討されている。現在さまざまな音源特定方法が検討されているが、どのような状況にも適する方法は存在しない。発生源を特定する方法を選択する際には、どのような音が発生しているかを正しく理解することが重要になる。
発生源特定の方法は大きく分けて下記のようなものがあある。
代表的な3つの音源特定測定方法
①多点で測定するもの:音圧マッピング、音圧インテンシティ
騒音計などの測定によって多数の点で測定し発生している音をマッピングするもの。
②ビームフォーミング
マイクロホンを複数配置した測定器を用いて測定し、位置や入射角度・音速などを考慮して分析を行うもの。
③音源ホログラフィ、
格子状のマイクロホンアレイを用いて測定し、分析を行うもの。
それぞれの発生源特定方法のメリット
①音圧マッピング
・測定に必要な機材が少なく費用が比較的安価
②ビームフォーミング
・短時間で測定できる
・高周波の測定が可能
・同定範囲が広い
③音響ホログラフィ
・短時間で測定できる
・結果の信頼性が高い
・空間分解能が優れている
対象物のサイズと周波数による使い分け
・ビームフォーミングが適する:対象物が大きいもの(おおむね2m以上)を超えるもの、周波数が中域以上のもの
・音響ホログラフィが適する:対象物が小さいもの(おおむね4m未満)、周波数が中域以下のもの
参考
音には大きく分けて3つの重要なパラメーターがある。このうち音源の特定に用いられるのは音響インテンシティと音圧である
1.音響パワー:音源から発せられる音の「単位時間あたりのエネルギー」
2.音響インテンシティ:音のエネルギーの量と方向をあらわす「ベクトル」
3.音圧:音圧の変動を表す「スカラー量」

【著者情報/略歴】2014年より日本騒音調査カスタマーサービス部門、HP記事担当。年間1,000件を超える騒音関連のお問い合わせに、日々対応させていただいています。当HPでは、騒音に関してお客様から、よくいただくご質問とその回答を一般化して紹介したり、当社の研究成果や学会(日本騒音制御工学会等)に寄稿した技術論文記事をかみ砕いて説明させていただいたり、はたまた騒音関連のニュースを解説させていただいたりしています。
ご意見やご要望は、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
問い合わせフォーム(クリックでページに移動)